ロッキード事件の裁判に専従していた1980年、特捜部副部長に昇格。83年論告求刑を終えると、法務省刑事局総務課長に発令、翌84年法務大臣官房人事課長。私と同期で、同じ時に特捜部副部長となった山口悠介検事は、官房人事課長志望だったのに特捜部長となり、特捜部長になるのが夢であった私は、官房人事課長となった。頂上の一歩手前で夢ははかなく消え去ったのである。
「それでも、ここまでやらせてくれた検察には、ご恩返ししなければならない」。私の中の理性人間ホッタ君の主張に従って、人事の仕事に励むことにした。当時は検事の数が足りない時代であったが、私は特捜部の検事だけは増員して戦力アップを図った。
次に、腹を決めて取り組んだのが、この連載の書き出しで触れた司法改革である。
当時、司法試験の合格者は5百名以下で、日本の法律家は圧倒的に数が少なく、多くの国民が法の保護を受けられずに泣き寝入りしていた。国際社会でも、日本企業の法的利益が守られず、欧米諸国に甚だしく立ち遅れていた。合格者の平均年齢は29歳。いつ受かるか見込みが立たない状況をみて、試験への挑戦をあきらめる前途有為な若者が増えていた。
私が改革を言い出した時、誰もが無謀だと止めた。「よし、やろう」と言ってくださったのが事務次官の筧栄一さんである。伊藤栄樹検事総長も最高裁事務総局も、最終的には了承をしてくれたので、私は日本弁護士連合会に諮ろうとしたが、当初は会ってもくれない。「検事が足りないから増やしたいんだろう」の大合唱で、加えて人権派の弁護士たちは、「増員すれば一般事件からの収入が減り、するとそれを原資として救うべき人が救えなくなる」と主張した。恥ずかしげもなくそんな主張ができるものだとあきれたが、今でも似たような主張をしている。
当時としては画期的だったが、私は各界各層の有識者による懇談会を公開で催し、ここで私学や司法書士会、塾などにも意見を述べてもらって、議論の幅を大きく広げ、国民の前に提示した。狭い法曹ギルド内の議論を、司法の利用者である国民各層に開放したのがよかった。弁護士会も、やむをえず参加するようになり、何とか対話ができるようになった。その段階で、私は甲府地検検事正の発令を受けた。88年、私はすでに54歳になっていた。
(東京新聞2008年 3月12日夕刊『この道』掲載) |
|
![]()
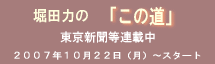

![]()